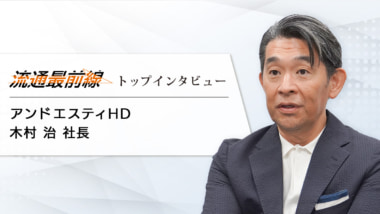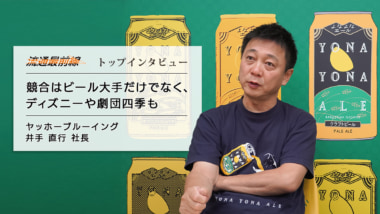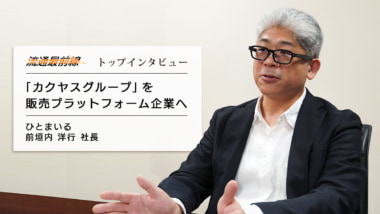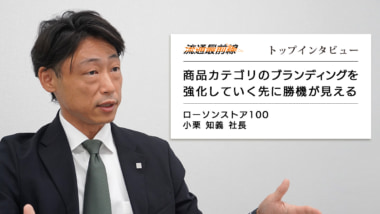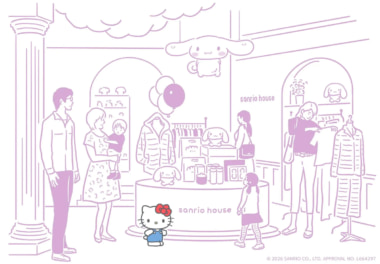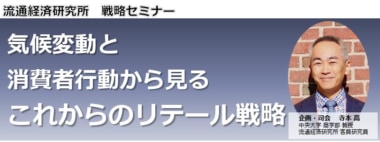コロナ禍を経て事業規模を縮小したペッパーフードサービス。一度は経営危機を迎えるも、2代目・一瀬健作社長の新体制により組織を立て直し、2024年12月期の決算で黒字化を達成した。現在は、主力業態「いきなり!ステーキ」の再拡大を図り、新業態・M&Aにも挑戦している。現状と今後について、一瀬社長に話を聞いた。
規模縮小して黒字化、ランチメニュー・コラボ企画で集客図る
――いきなり!ステーキの現状についてお聞かせください
2025年の5月末時点で173店まで店舗を縮小して、黒字を達成しました。今後の出店戦略としては、繁華街立地への再出店した後、地方においても営業店のある都道府県から中心に、もう一度ロードサイドや一定の基準を設けた地方都市への出店を考えています。
かつてコロナ環境の中で会社を継続させるために物件を整理して資金を回収し、新宿や渋谷など、都心の繁華街立地から撤退せざるを得ませんでした。もし仮にコロナが明けるまで継続的にお店が営業できていたとすれば、今でも全店舗の中で売上・利益ともに非常に大きく貢献する場所になっていたと思います。
そのためエンジンをかけ直して物件の募集活動に取り組み、さまざまな情報を集めています。いきなり!ステーキが再成長していくと認識してもらうためにも、繁華街立地への出店戦略を進め、既存店のボトムアップも狙っていきたいです。
――現在の客単価は
2000円ほどで、いきなり!ステーキの創業時とさほど変わっていません。当時は100g500円でしたが、肉マイレージ※のランク争いによってお客様単価が高くなることがありました。ただ2000円という価格帯が昔から1つの軸となっています。
ハレの日向けのメニューだけですと、どうしても客足が遠のくため、最近では、商業施設店舗でステーキ以外の販売にも注力しています。チキンやハンバーグであったり、牛のバラを使った牛カルビ定食をリーズナブルな価格で用意しています。既存の路面店にもランチセットがあります。
ラーメン店の「1000円の壁」と言われるように、ランチの相場が上がる中、しっかりと私達のランチ価格帯があることによって、週5日間ランチを外で食べる際に、1回でも思い出してもらえるようになりたいです。ハレの日以外にも、日常食として利用していただきたいです。
※食事金額に応じて付与されるポイント制度。クーポンが付与されるなどの利用者特典が受けられる。
――最近は他社とのコラボレーションにも取り組まれていますね
IPコラボであったり、他社とのコラボであったり、去年ぐらいから新たなお客様を獲得するための取り組みを進めています。ホロライブさん所属のVtuberとのコラボであったり、5月には名古屋エリアで展開している「がブリチキン。」とコラボしました。
これまでの「いきなり!ステーキ」のキャンペーンフェア商品といえばステーキ肉でした。でも「がブリチキン。」とコラボするという名目があると、チキンを前面に出したキャンペーンを打つことができて、いきなり!ステーキのチキンもリーズナブルで美味しいということを伝えられます。来店動機・頻度の向上につながれば、新規の顧客を確保できます。
いきなり!ステーキのお客様は40~50代のお客様が多く、創業時からのお客様は60歳を超えて定年される方もいらっしゃいます。世代が上がる中で卒業される方もいます。全体のお客様数としては少ない10代~30代に対し、いかに来店動機を提供していくかが大事。そのための準備をしっかり行い、永続的な企業を目指しています。
――海外フランチャイズの状況は
上期の中で4店舗増えており、既存のオーナーが積極的に出店を考えているため、年内にあと3店舗ぐらいプラスになる予定です。海外3カ国で累計10店舗を越える見込みがあり、特に台湾が好調でコロナ前の売上高に近づいています。お客様数が減っている所もありますが、お客様単価が思いのほか高く、力強く成長しています。
品質にこだわり、店舗DXにも注力
――仕入れの手順・工夫は
年に1回、オーストラリアかアメリカどちらか1カ国に出張しています。今年はアメリカで現地のパッカーまたは食肉メーカーと直接お話しする時間を設けました。私たちの考える安定経営のために、長期契約をこれぐらいの価格で結ぶためには、どのような部位・調理・提供方法が必要かを現地の方と一緒に考えます。
契約期間が長ければ、年次予算を組む時に原価変動のリスクをあまり考える必要がありません。例えば1年間の食材の契約が取れていたとしたら、年度の値上げはしなくても良いですし、原価変動はほぼ考えなくていい。ただそれが期をまたいだり、短期の時もあったりすると、予算を組む段階で大きくブレる要因の1つになります。
――スケールメリットはありますか
今の(牛肉を扱う)チェーン店のスケールメリットは、すごく薄くなっていると思います。牛肉輸入の自由化後、1994年にペッパーランチを作った頃、輸入牛はまだまだ買われていないから安かった。現在、一般的に海外の牛肉が主流化している中で入手するためには物流を増やさなければいけません。
一方、BSE(牛海綿状脳症)の問題もあって、日本規格が世界基準よりも厳しい基準であることから、対日向けに作りたがらないという事情もあります。そうしたこともあり、海外からの輸入量が制限されています。でも牛肉を扱う事業者は、どんどん増えている。量が無いため取り合いになった結果、相場が上がってきているという状況が、この数年ずっと続いています。
焼肉屋も増えました。倒産件数が多いと言っても、それは淘汰された所で、まだまだ伸びている所もあります。そういう牛肉リスクを分散するために、お客様が求めるもの以外にもメニューを増やしていくことで牛肉の量的なバランスを取る。でも粗利高が各々異なるため、今までの薄利多売のビジネスから、少なく売って大きい利益を取るという逆転の発想に変えざるを得ない分岐点が出てくる。
その分岐のお客様数にならなくなった瞬間から赤字になります。そうすると原価を上げなければいけない。海外に出向いていくことによって向こうの工場やパッカーさんとかとお話して、そういった日本の事情も説明して、商品を提案していただいています。
――品質についてどう考えていますか
品質を落として価格を抑えていくようなことは基本的にはしません。ただし、産地の見直しは考えています。例えばオーストラリアでは、南と北で草の生え方が異なります。グラスフェッドを食べ比べると味が全然違う。食べさせているものにも着目して、工場などを見直すことによってクオリティを維持し、価格を抑えています。
絶対、お客様に品質を下げた物を出さない。これは先代からの教えというか、絶対的に外しちゃいけない事だと、当社の全員がそう思っています。高い品質と、ステーキとしてはリーズナブルな値段にこだわっています。
ステーキは今でも日常食ではありません。その中で、どのチェーン店を選んで食べようかなと思った時に、一番に思い出してもらうお店で在り続けたいと考えています。
――今後の利益・客数はどう確保しますか
原価がこれだけ上がっている中で、店舗のDX化を時代に合わせて進めていく取り組みをスタートさせています。人件費を抑制するのではなくて、店舗の回転率を上げていくという考え方です。
他よりはちょっとリーズナブルで品質の高いステーキが食べられるというコンセプトを崩さずに、お客様数を取るために、DX化による回転率を上げてピークタイムの最大値を上げていく。レジ等のシステム周りも改善し、1時間当たりの生産性を高めます。
加えて、人手不足の中でも人の入れ替えが激しい中で、調理技術でも何かDXのようなものが導入できないかと考えています。商品のクオリティが上がることが大前提で、素人でも容易に技術が習得できるようなもの。温度と時間の2つが均一に管理できるような仕組みを考えています。
どの店でも同じクオリティーを保つことが、飲食店としての大義であると考えます。そのためDXを寒々しいものにはしたくない。どこかで一時加工した物を店舗で温めるのではなく、やはり店舗での手作り感であったり、シズル感であったり、人が作業するという点は残しながら美味しさを演出し、クオリティーを上げることにこだわりたいです。
新業態「すきはな」のトライ&エラー、M&Aで海鮮に挑戦
――2024年12月にオープンした新業態「すきはな」の現状は
いきなり!ステーキのペッパフードサービスが新業態を始めたということで、いろいろと賛否がありました。当初使っていた国産のリブロースは、非常に大きな部位で、すき焼きとしては厚切りで提供していました。しかしオープン当時、多くのお客様に食べてもらうよりも前に「お肉の量が少ないんじゃないか」「野菜がないじゃないか」といったアンチコメントが先行し、少し炎上しました。
お客様の声は、もちろん私も見ていますし、毎日のようにネットニュースの口コミも全部目を通しています。そういった口コミの中で悪評とされているもので、当社としての品質を落とさずに変更できる部分に関しては、どんどん改善を図っている最中です。
メニュー面では、当初は「国産牛」※を安価で提供することも売りの一つでした。サーロイン・リブロースという油身と赤身がしっかり混合された美味しいお肉の部位を使いたかったのですが、美味しくないという意見も頂いてしまって。美味しいという意見も勿論ありましたが、すき焼きに合うお肉を仕入れ直し、国産牛を全部「和牛」に切り替えました。
提供の仕方についても、グラム数を変えずに枚数を増やしています。会食やカップルのデートで使って頂くために、コースメニューも新たに導入しました。
※国産牛は、和牛以外の牛で、日本国内で飼育された期間が最も長い牛。
1号店は、ランチを求められるサラリーマンもいらっしゃるエリアなので、新橋の価格帯に合ったランチメニューを4月後半に導入しました。卵とじ丼は、味噌汁・サラダも付けて税込1200円です。牛すき焼き膳(1500円)も人気で、口コミで利用者が増えてきています。
ですが、季節の影響を受ける業態でもあります。猛暑になってきて、すき焼きというキーワード自体が、Googleトレンドから検索数が減っているのを見ているので、今の時期にこれまでお客様から批判を受けていた箇所の改善をどんどん図っています。お野菜を食べたいというお客様のニーズに応え、せいろを使ったメニューを開発している最中です。
お客様のニーズを無視することはできません。まだ利益が出ているわけでは無いので、夏場を改善の期間として上手く活用し、新業態を育て、すきやき需要のピークと言われる冬の11月頃に向けて最大値を目指したいと思っています。
――牡蠣居酒屋「かいり」M&Aのきっかけは――
今年の3月に牡蠣居酒屋の「かいり」をM&Aで取得しました。恵比寿に1店舗、渋谷に2店舗の計3店舗あります。ステーキと真逆の海鮮系ということで、外食をやる上でのリスク分散を考えました。新業態を始めるに当たり、既存店の閉店やスクラップ&ビルドは全く考えていません。あくまでも新しい事業柱になる、または成長路線に乗せられる業態を考えて選びました。
会社が1つの業態を立ち上げるのには、非常に労力を使います。ですが組織を再び成長させ、売上と利益にこだわるためには、さらに新しい事業を展開していかなければいけない。路面でなく、家賃が抑えられる空中階や地下にも出店できて、先々は全国に広く展開出来るような業態をM&Aで取得することで組織体制を守り、生産性を上げるという目的もあります。
今まで、いきなり!ステーキやペッパーランチの2業態を繁華街に出店する際には、地上1階での出店が望ましく、2階や地下に出店する場合には、入口・間口が広く取れる動線があるなど条件が限られていました。かいりを取得したことで、いきなり!ステーキの物件を探しながら、かいりの物件も一緒に探せるようになり、物件を探す労力が分散しました。
また、「かいり」で提供している海老やアワビを、すきはなのコース料理に加えられるという仕入上のメリットもあります。
「従業員の幸せなくして会社の発展なし」
――経営で一番大切にされていることは
「従業員の幸せなくして会社の発展なし」というのを一番のポリシーとしています。従業員が「働いてて良かったな」と思える会社にしていきたいという想いがあって、株主やお客様に還元したり喜んでいただくためには、まずはそこで働く従業員の幸せなくして会社の成長は絶対にないと思っています。その幸せのために、社長にしかできない決定を行う必要があると考えます。
父の考え方は、売上・利益を上げる事によって店舗数を拡大し、上場企業になることで、そこで働く人たちのステータスを高めることで、金融機関からの住宅ローンが下りやすくなるとか、親族にここで働いていることを報告できるとか、成長路線に乗せることによって、従業員皆さんの給料や働くポジションを増やしていくというものでした。
一方、私が引き継いだ時には、店舗数を縮小している最中でした。でも従業員を幸せにしていくことを考えると、これ以上店舗数を減らさないためには、新たな事業柱を育てるなど新たな挑戦が必要になる。
そこで皆でアイデアを出しながら、自分達がその会社の経営であったり、売上であったり、お客様の喜びにつながるアイデアを合わせて出しているんだという一体感を醸成することが従業員の幸せになると思いました。
小さな成功を積み重ね、その先の中の利益を皆で分配しながら会社の利益を積み、その先には店舗数を拡大していく。海外にも直営店を設け、もしかしたら海外で仕事をしたいという人達の思いも叶えていけるという成長路線のシナリオを描いています。
――先日、7月からの賃上げを発表されましたね
前期に黒字化して以降、ようやく発表できました。コストが上がる中で、黒字化と給与を増やせることは比例しません。アルバイトの時給も最低賃金相場が全国的に上がってきている中で、最低賃金で募集活動できる場所なんてありません。私たちの働く環境下は繁華街立地であったり、商業施設内であったり競合他社が多いところで、採用活動のハードルも高いです。
かつて会社がピンチの時に、福利厚生を減らし、賞与も出せず、早期退職者を募ることもありました。それでも残って下さった方たちもいらっしゃるので、そういう方たちにお金の面で報いたいと考えています。
株主への配当還元も大切ですが、今後また成長していくためには、人というところが一番大事だと思います。やっぱりボーナスやお給料という所で報いていくことが本当に大事です。来期に向けて、しっかりと成果を出せるようにしていきます。
■一瀬健作社長略歴
生年月日:1972年6月26日
1993年4月:さわやか入社
1999年11月:ペッパーフードサービス入社
2005年3月:取締役ペッパーランチ運営部長就任
2012年1月:取締役管理本部長兼CFO就任
2012年1月:専務取締役管理本部長兼CFO就任
2019年1月:代表取締役副社長管理本部長兼CFO就任
2020年6月:JP(現 ホットパレット)取締役就任
2022年8月:代表取締役社長CEO兼管理本部長兼CFO就任
2022年8月:代表取締役社長CEO就任
取材・執筆 古川勝平
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。