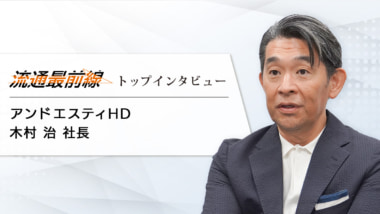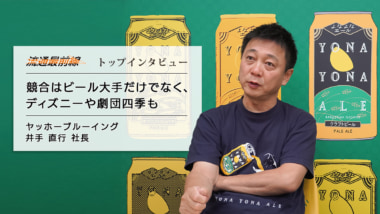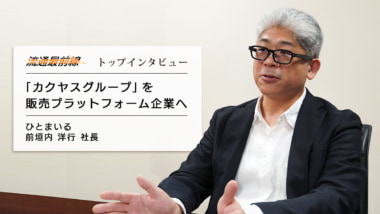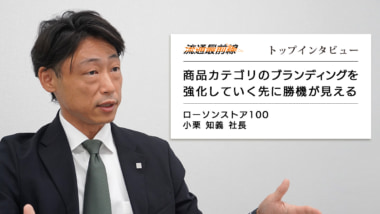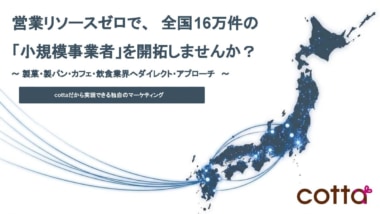回転寿司業界No.1の売上を誇る「スシロー」の強さについて、前編では、うまい寿司を出したいスシローのDNAや社員のモチベーションを維持する労働環境が明らかになった。中編では、ファンド傘下でのマネジメントの実際やスシローの創業期を知る社員から社長になった豊﨑賢一前社長から、コンサルタント出身の経営者として社長交代した後、どうスシローをマネジメントしたのかを語ってもらった。現場に発信した最初のメッセージは意外にも「やんちゃ、やろう」だった。
■クビも辞さず、ファンドに対してもモノをいう経営
――コンプライアンスを守る面では、ファンドのメリットがありましたが、逆にファンドのデメリットは何ですか。
水留 これはファンドが、という問題ではないですが、やっぱりファンドの下で働くマネジメント(経営陣)がどうしても、ファンドを見すぎてしまうことがある。株主はファンドであり、ファンドに経営陣の生殺与奪権がある。ファンドは、社長をクビにしようと思ったら、クビにできてしまう。そういう中で、忖度するというか、ファンドを向いたマネジメントになりがちになる。これはスシローがという話ではありませんが、一般論として出てくる話です。
――水留社長のファンドに対するスタンスはどんな感じですか。
水留 僕は簡単です。クビにしたければすればいいじゃん、という考えです。それは自分の考え方として、自分にマーケットとしての価値があれば、別にクビにされたってどっかが引き取ってくれる、くらいな気持ちで生きていればいい。たまたま私はいろんなところをやってきたんで、そういう発想がある。
一方で、やっぱり、その会社しかいなかった人からすると、そこに対する不安というのは、すごく強いわけですよ。外に出された時に、自分がどういう風に評価されて、次はどういう風にあるのかとか。やっぱり自然に不安になると思う。そういう意味で、ファンドを見すぎてしまうこともあると思う。
――ファンドは、企業を安く買って高く売るイメージがありますが。
水留 今の世の中は、ファンドが企業を安く買えない時代になっている。ペルミラの時もそうですけど、何社もの中から一番高く札を入れた人が買うわけです。今は、高く買って高く売りたい。買い手のファンドは、どうしたら企業価値が上がるかシナリオをもっている。シナリオがあるから、この値段で買っても自分たちは損をしない、利益がでるというストーリーをもって買いにくる。闇雲に買っているわけではない。
――経営陣の派遣以外にファンドが持つ機能にどんなものがありますか。
水留 ファンドが持っているシナリオがあるので、シナリオに対して支援をする感じです。もちろん、シナリオを実行する経営陣を選ぶ。既存の経営陣でそれができると思えば、変える必要はない。もちろん、資金の支援もする。
非上場化してファンドの傘下にいる期間というのは、ファンドしか株主がいないので、配当する必要がない。配当を視野に入れているファンドもあるが、彼らはどちらかというと配当で利益を上げるという発想ではなくて、ある程度の投資をした上で、その先の企業価値を上げるという発想をする。基本的にはキャピタルゲインで投資を回収する。
――ペルミラの時代は、ファンドの資金を何に投資したんですか。
水留 ペルミラの時代は、ファンドの資金を出店に使いました。ずっと、20店くらいだった出店数を30店とか40店近くまで上げた。当然、それには資金が必要なので、出店に資本を集中して、成長を加速して、その先のキャピタルゲインを大きくしていった。
――回転寿司の出店資金はどれくらいですか。
水留 回転寿司の出店では、1店舗あたりで億を超える投資が必要です。うちは原価率を約50%使っています。競合が仮に同じように50%の原価率を使おうとすると、スシローぐらいの1店舗あたりの売上がないと、なかなか利益はでない。
まったく無名のところが、スシローとおなじフォーマットで出店しても、お客さんは、取れない。そうすると絶対、利益はでないんですよ。だから、新規参入は難しいんですよ。売上があるから、原価率がかけられ、利益がでるという循環モデルがある。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。