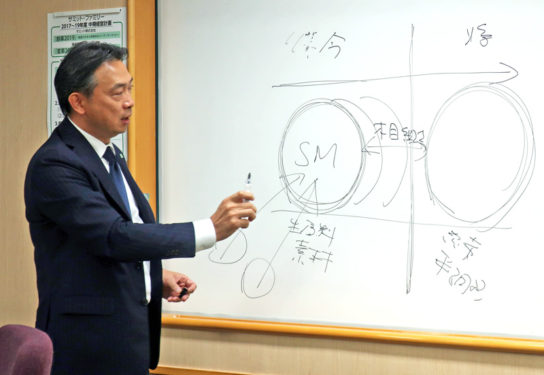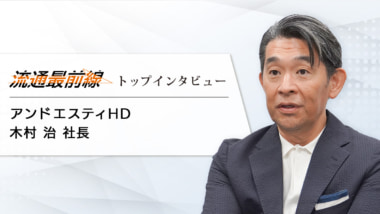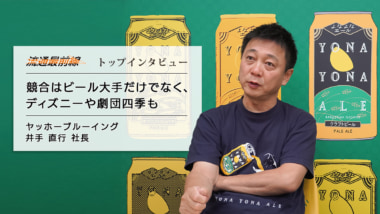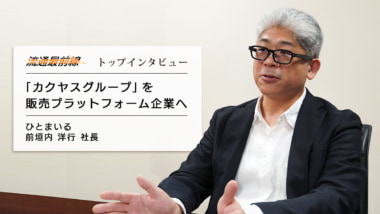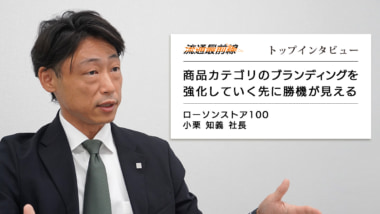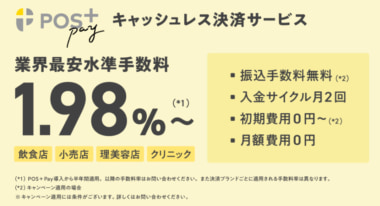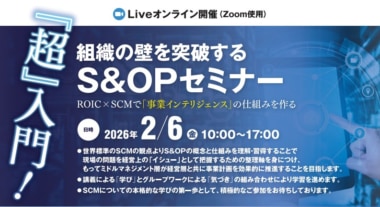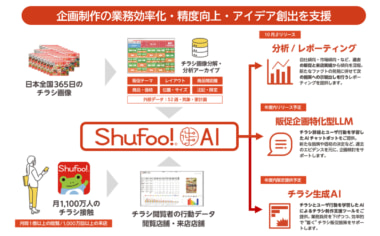――ECサイトが成長する中で、リアル店舗の優位性はどこにありますか。
竹野 スーパーマーケットもアマゾンにすべて食い尽くされるみたいなイメージがマスコミ報道でされるが、我々は生きる道がいっぱいあると思っている。
スーパーマーケットの中で独自性を出していく。独自性とは、簡単に言えば、「時代にあった店をいち早く作って、お客様に共感していただいて、来ていただけるお店を作る」ということだ。
日常の中で、実際に見て買うことができる生鮮食品というのは、やっぱりネットでは一部の人しか機能しない。本当に忙しい人や病気になってしまった人とか、本当にお金持ちの人とか、いまの段階では、マスにはならないだろうと思う。
だから、アマゾン怖いから、うちもEコマースをガリガリやらなきゃダメだとはならない。時代にあったスーパーマーケットを作ることによって、お客様をほかのスーパーマーケットから取る、ほかのドラッグストアから取る、ほかのコンビニから取るということで、成長は十分担保できる。
本来は、そこにスーパーマーケットの良さがあって、強みがあって、すごみがある。そこをやっていきたいと思う。なので、あまりECに脅威はないと思っている。
――かつて運営していたネットスーパーの課題はなんでしたか。
竹野 配送コストが払えない課題があり、配送コストを誰が負担するのか。それを誰も許容する社会ではない。その一言だ。配送コストが許容されれば、日本でもネットスーパーは、基本的にはやれると思う。
ラストワンマイルが、欧米に比べてお金がかかるというのが、決定的な差だ。生協さんみたいに仕組みができていて、それがコストとして吸収できる人たちは、慣れてるからやっている。
やるかやらないかは別として、私の頭の中では、単に店頭に商品を取りに来るよりも面白いことをやろうと思っている。お店をコミュニティにしようとかは、そういうところの手前にある施策となっている。
――アマゾンフレッシュが拡大していますが。
竹野 それは、勝手にやってくださいという感じだ。アメリカで、アマゾンゴーを何時間か張り付いて見ていたが、車が10分くらいに1台きて、スッと帰っていく。これが本当に採算とか商売にあうのか。
それだったら、うちはその瞬間に何百人というお客さんが来店している。そっちをしっかりやった方がいいんじゃなの、ということだ。
彼らはデータを集めたりとか、壮大な実験の中のひとつがアマゾンゴーであったり、アマゾンフレッシュだったりする。黒船が来て死んでしまうことはない。
時代の要請への対応として、惣菜であれば、「できたて」「焼き立て」「作りたて」「切りたて」、そいうったことが、徹底できればいいと思う。だから、そこにこだわってやっていく。
惣菜は絶対、最後は、「揚げたて」「できたて」でやりたい。そこが多分、未来のスーパーマーケットの生命線になるので、そこを磨き上げるのが、いまアマゾンに対抗するよりは重要なことだと思っている。
――食品の購入先が、EC、ドラッグ、コンビニなど多様化する中で、食品スーパーが抱える課題は何か。
竹野 マクロから見ると、スーパーマーケットが負けてる、攻められてるという話かと思う。戦い方はいくらでもあって、時代の要請にあっていけば、全然、課題感はない。
昔、今、将来と、時代が変わる時間軸がある。今、大抵のスーパーマーケットは、生鮮があって、素材とか生原料素材が多い。これが、ドラッグストアだとか、コンビニとかに攻められている。
単純に、キャベツだったら丸1個を売る、肉だったら生肉を売るという状況がある。これだったら、誰でも仕入れられる。
だけど、サミットは、惣菜だとか、半調理品だとかを強化して、将来へ向かっている。この差が、まず普通のレギュラースーパーとの競争の中で、優位性となっている。
私は、これからの社会というのは、「使わない社会」「使いきれない社会」といっている。使わない社会というのは、料理するにも包丁も使わない、火も使わない、まな板も使わない、買い物行くにも車も使わない時代だ。
それからキャベツ一個買っても使いきれない。実際、三田店では、こんな大きな1200円シャインマスカットがあって、それよりも売れているのは、同じものを半分に切ったシャインマスカットだ。
なぜかというと、一人世帯では食べきれない。だから、そうやってきめ細かくやるということが大切だ。きめの細かさが差につながる。これを保ってるかどうかで、未来が分かれる。
――コンビニやドラッグストアへの対抗策は。
竹野 コンビニ、ドラッグストアがいま、生鮮食品を取り扱っていて、多分、地方なんかは競争が激しい。それに、コンビニ、ドラッグストアも、もっともっと加工度を上げてくる。
でも、スーパーマーケットには、店舗のサイズだとか、バックヤードだとか設備が整っていて、できたて、揚げたてをつくることができる。
セブン-イレブンはいい工場を持って、おいしい惣菜を作ってるが、できたてじゃない。やれるのは、唐揚げを揚げるか、コロッケを揚げるかだろう。
大量にいろんな種類のコロッケを作って、温かい状況で提供できるのは、コンビニの仕組みではできない。だから、絶対にこの差がある。
素材を売るだけでは、やられてしまう。でも、揚げたての惣菜を提供するように、絶対、追いつけない敷居があると思う。
――惣菜の具体的な強化策は。
竹野 一つは、大惣菜プロジェクトを進めている。例えば、青果で売っている1個のキャベツが、ざく切りになっていたり、ロールキャベツで巻かれてたりしている。
「おいしいね」って言える生原料が、実は、店舗の惣菜でも使ってるといったら、お客様にとって、こんな便利なことはない。
その時の気分で、「今日はちょっと疲れたからロールキャベツ買っちゃえばいいや」、「今日は息子の誕生日だから、ロールキャベツ作っちゃおうか」という時は、原料から買いたい。
疲れた時は作ってくれている惣菜がある。丹精込めて作りたい時は、すごいいい素材がある。それが、お客様の共感だとか、満足だとか、来店動機につながってくる。
これは、いま限られたスーパーマーケットにしかできていないので、我々の競争優位の戦略になってる。
――大惣菜プロジェクトの狙いを教えてください。
竹野 大惣菜プロジェクトの目標は、上位10店舗で大惣菜プロジェクト対象アイテムの売上高が、全売上高に対して25%以上となることだ。それが突破口となって、全体を引っ張って、そこでやれたこと、やれないことが全体に波及すると思っている。
ただ、一つ目標値をつけただけなので、ゆるい目標だ。いま、上位3店舗が20%を超えているので、このまま進んでいけばいいと思っている。
――惣菜を強化するための具体的な施策は。
竹野 精肉の加工を行う生鮮センターを新設したことが一つの施策だ。生鮮センターで加工した肉を販売する店(完全PC店舗)、精肉を店内加工をする店、両社のハイブリッドの店を作る。
そうなると、ハイブリッドと完全に生鮮センターの精肉商品を販売する店舗は、当然、人が余ってくる。完全PC店舗やハイブリッド店舗は、小型店だったり、中規模売上店で、惣菜に人が回ってない店が多い。
精肉部門の人員は、惣菜を揚げたり、焼いたりする、グリルキッチン(精肉部門の素材を使った惣菜コーナー)のスキルがあると思われるので、親和性があると思う。
いまのパートさんや社員が、惣菜にシフトしてもらうことを地道にやるストーリーも考えている。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。