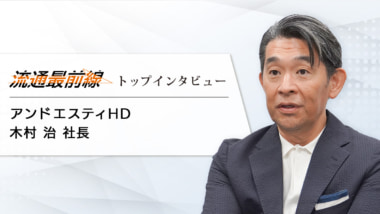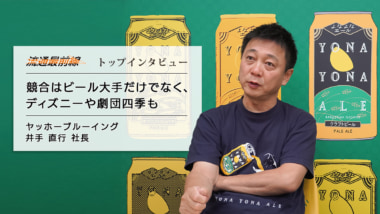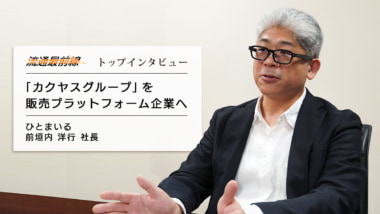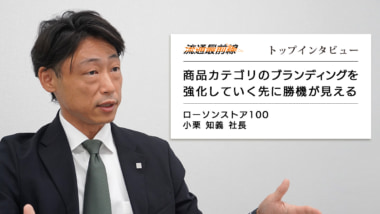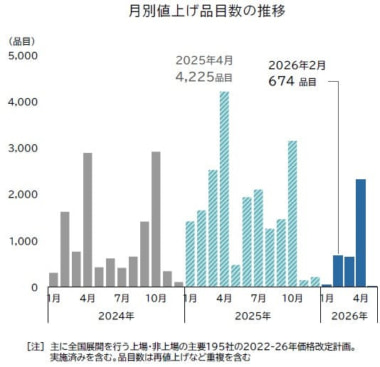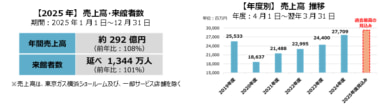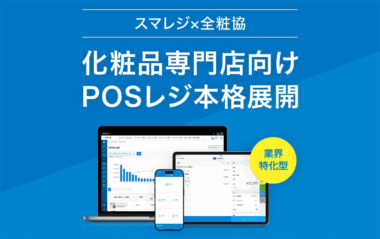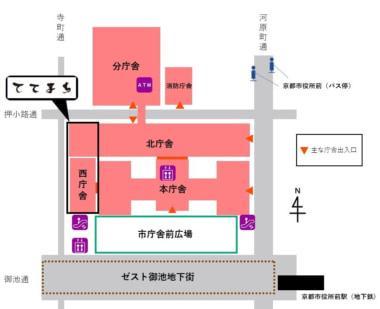回転寿司業界No.1の売上を誇る「スシロー」の強さについて、前編では、うまい寿司を出したいスシローのDNAや投資ファンドがもつ機能などを明らかにした。中編では、寿司職人であり現場を知り尽くした豊﨑賢一前社長から社長交代した後、どうスシローをマネジメントしたのか、当時を振り返った。後編では、9000億円ともいわれる未開拓の寿司市場の開拓を目指した新業態開発や元気寿司との経営統合のメリットについて語ってもらった。
■9000億円の未開拓の寿司市場を新業態で開拓する
――成長戦略として、新業態を開発する狙いは何ですか。
水留 新業態を開発する狙いは、いまのスシローの客層や利用シーンを拡大することです。今は、郊外ロードサイドの店舗が主流で、車がないと来店できないこともある。また、夜にお酒をゆっくり楽しみながら寿司を食べるという利用シーンもあってもいいと思っている。
いま、統計的に言うと、寿司のマーケットというのは、1兆5000億円くらいと言われています。そのうち100円の回転寿司の市場規模は4500億円。グルメ系の回転寿司の市場規模が1500億円で、回転寿司の市場規模は6000億円と言われている。
残りの9000億円という市場が、回転寿司ではないところにあるんですよ。もちろん回転寿司が大きくなることで、9000億円から回転寿司にシフトしていく部分もありますし、一方で回転寿司では手が届かない部分もあって、それをどういう形で取りに行くのかというのが新業態の中で考えなきゃいけないことです。
――9000億円というのは大きなマーケットですね。
水留 回転寿司の隣に大きなマーケットがあるんですよ。このマーケットは、銀座の寿司屋さんのような、客単価2万円、3万円の世界ではないんですよ。そこはそんなに行く人がいないので、マーケットはあまりない。
マーケットはどこにあるかというと、住宅地だとか、駅前だとかに普通にある、お父さん、お母さんがやっているようなお寿司屋さんですね。職人さんを1人か2人くらい使っているような。どちらかというと、後継者がいないとかいろいろあって廃業している。いま、お寿司が食べたくても、食べる場所がないという人が出てきているんですね。
――豊﨑前社長が開発した新業態「ツマミグイ」(2015年1月出店、2016年6月までに全店閉店)を閉店した理由はなんですか。
水留 飲食というのは、百発百中の世界ではないんですね。なので、「ツマミグイ」を閉店したのは、前社長を否定したわけではありません。うまくいかないものは辞めましょうというそれだけの話です。新業態はいくつもアイデアを出していって、その中で生き残るものを残していけばいい。
「ツマミグイ」は利益も出ていたが、数百店という出店には向かない業態だった。1号店の中目黒店は意外と場所として広いんですよ。あの場所で、たまたま物件があった。ああいう物件って世の中に、なかなかない。そうすると、開発ができるかというと、難しい。
ある程度、駅前ならこういう物件ってあるよねという場所で、成立するような業態を開発していかないと店舗数は増えない。
――水留社長就任後に開発した新業態「七海の幸」(2015年11月開店、2016年6月閉店)を閉店した理由はなんですか。
水留 「七海の幸」はツマミグイを閉店した後の中目黒の物件を何とかしなきゃいけなかったんで、別の実験もしようかということで、看板を変えてやってみた。「七海の幸」は利益を出すというよりも、どちらかというと、どういうメニューとか、どういう寿司としてのレベル感というか、グレードが、どういう風に反応するのかをちょっと実験した。「七海の幸」はいい食材を使ったんですよ。それで、どれくらい客単価が取れて、どういうお客さんが付いていくかというのは、それなりに分かったんで、物件はお返した。
――新業態のイメージとして固まっているものはありますか。
水留 ありますよ。もちろん、いろんなものを開発していこうと思っていますからね。その一つとして、フードコート的なところに、出せるようなフォーマットを作るというのをいま現場は、やっている。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。