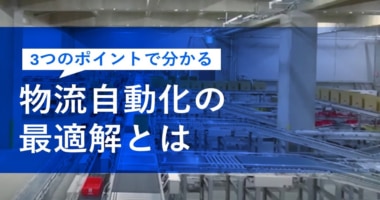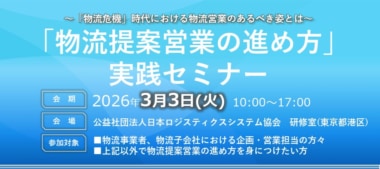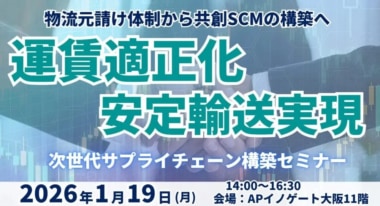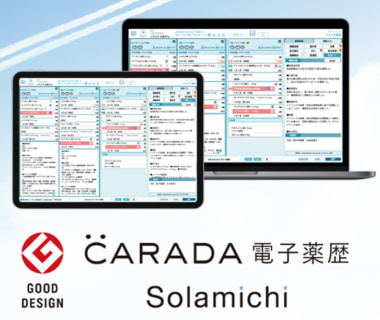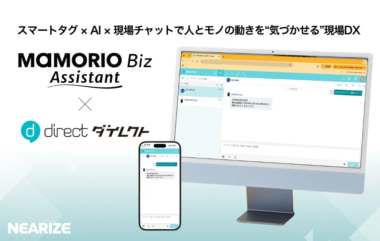【連載】冷凍食品の現在と未来 第6回霞ヶ関キャピタル/進化する冷凍倉庫
2025年10月24日 10:30 / 経営
冷凍食品市場は今、共働き世帯の増加やタイパ意識の高まりなどを背景に大きな盛り上がりを見せている。この拡大する市場を支えるインフラとして、コールドチェーン(低温物流網)の重要性が高まっている。不動産デベロッパーである霞ヶ関キャピタルでは、最新の冷凍倉庫によって冷凍食品の消費拡大を後押しする。
第5回吉野家はこちら
3つのエリアに物流倉庫を開発、コールドチェーンを「面」でつなぐ
霞ヶ関キャピタルは、2020年に物流施設の開発に着手して以来、冷凍冷蔵倉庫市場で存在感を高めている。これまでに、冷凍冷蔵倉庫やチルド倉庫、3温度帯倉庫、冷凍自動倉庫を計10物件竣工しており、さらに現在も冷凍自動倉庫など6物件を工事中、2物件が設計進行中と、開発を加速させている。
冷凍倉庫開発のトレンドとして、霞ヶ関キャピタルは3つの立地を戦略的なキーワードとして掲げる。
1つ目が「湾岸エリア」だ。古くから冷凍倉庫が密集しており、港が近いことによる輸入品の取り扱いが多いこと、また密集地であるためトラックの混載がしやすく効率的な運行ができるというメリットから、関東、関西、中京圏、九州など、いずれのエリアでも依然として人気が高い。
2つ目の立地が「内陸エリア」。従来は上述の通り湾岸エリアが冷凍倉庫の中心だったが、昨今では消費地に近い内陸エリアでのニーズも増している。実際、霞ヶ関キャピタルでは大阪府茨木市や横浜市都筑区で冷凍倉庫を構えている。
そして3つ目が「中継地点」。物流の「2024年問題」に代表されるように、ドライバーの労働時間の規制や配送の効率化が社会全体の課題となる中で、幹線輸送をつなぐ中継地点が注目されている。インフライノベーション事業本部副本部長兼開発第一ユニット長の小山哲迪氏は「当社は今、関東と関西のちょうど中間地点にあたる静岡県袋井市で倉庫の設計を進めている。車だと関東からも関西からも3時間半程度の立地。こうした中継地点になる場所も戦略的に重要」と語る。
冷凍食品は製造から消費まで温度帯を徹底的に管理することが求められる。その意味では、湾岸・内陸・中継地点と特色が異なる3つのエリアに物流拠点を配置し「点だけでなく面で開発することでコールドチェーンをつなげていく」(小山氏)という方針だ。
1パレット・1日から利用できる柔軟な短期保管サービスを開始
霞ヶ関キャピタルは、デベロッパーとしての側面を持つと同時に、物流会社の「クロスネットワーク」をグループ内に保有している。このグループ体制の強みを生かし、パレット単位で冷凍保管を提供するサービス「コールドクロスネットワーク」(CXN)を運営する。
例えば約1万m2(3000坪)の最小賃貸面積や、5年・10年の長期契約といった条件がネックとなり、冷凍倉庫を借りることができない企業は少なくない。CXNは、そうした需要に応えるサービスとして昨年11月に埼玉・所沢エリアの冷凍自動倉庫でローンチ。パレット単位で、1日から保管可能なサービスとして注目を集めている。
CXNで保管される商品としては、昨年の冬はクリスマスケーキやおせち、今年の夏はアイスクリームなど。通常の冷凍倉庫同様に季節変動はあるものの、「直近の7、8月は100%近い稼働率」(同)という。今後は、老朽化が進む既存倉庫の建て替えや、フロン規制に伴う設備入れ替えなど、一時的な保管先としての対応も可能で、多様な利用方法が期待される。
とはいえ、CXNのようなパレット単位で保管できるサービスは、1社のテナントに長期貸しするのに比べて、利用企業を広く募る必要があり運用面での負荷が大きい。それでもこうしたサービスには一定のニーズがあり、今後拡大していくポテンシャルもあるとみている。「実際に運営では大変な面もあるが、一度利用いただいた企業に継続して使ってもらい、それが広がることで、将来的には安定的な稼働を実現していきたい」(同)。
10月にはCXNの2番目の拠点として仙台の冷凍冷蔵倉庫も稼働。さらなる利用拡大を目指している。
今後の冷凍倉庫の注力ポイントは「環境配慮と自動化」
冷凍食品市場が拡大していく中、物流倉庫の側面では今後どのような点を強化していく必要があるだろうか。霞ヶ関キャピタルが今後の注力ポイントとして「環境配慮と自動化の推進」を挙げる。
冷凍倉庫は2030年のフロン規制を見据え、自然冷媒を使う環境に配慮した設計が各社の共通認識となっており、対応が求められる。加えて、冷凍倉庫の自動化を推進することで、マイナス25度という過酷な環境での作業を減らし、労働環境の改善と将来の労働人口減少を見据えた対策が必要になる。「人が働かなくても済むよう、可能な範囲で倉庫内の作業を自動化していくことが今後求められる」と小山氏は強調する。
そして最後に、冷凍食品を取り扱う流通・小売・メーカーが倉庫選びの際に見落としがちな点として、「電気代」について考慮することも重要だと小山氏は指摘する。
「冷凍倉庫は冷やす必要があるため、必然的にすごく電気を使う。老朽化した古い冷凍設備は省エネではないため、継続して使用した際の電気代は大きな負担となる。最新の自然冷媒を使用した設備を選ぶことで、電気代の負担を大きく軽減できる可能性がある」と述べ、比較的新しい倉庫を選ぶことも重要な検討項目としている。
取材・執筆 比木暁
【連載】冷凍食品の現在と未来 第1回イオンリテール/専門店「@フローズン」が好調
【連載】冷凍食品の現在と未来 第2回日本アクセス/チン!するレストランが大ヒット
【連載】冷凍食品の現在と未来 第3回味の素冷凍食品/「ギョーザ」人気の秘密を探る
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。