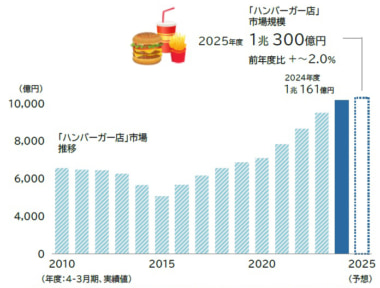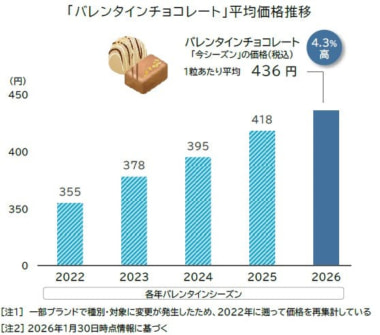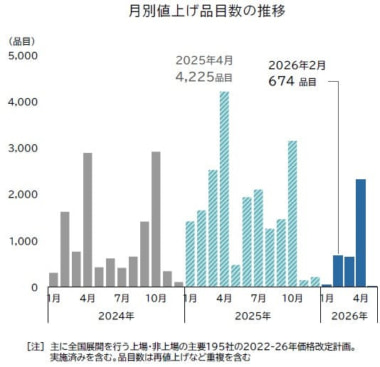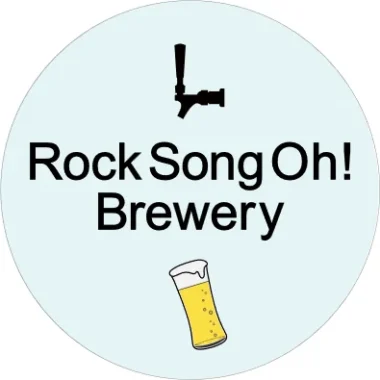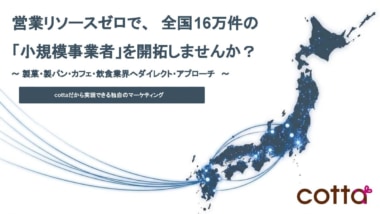クラフトビール/市場拡大で約6割のメーカーが増収に
2018年08月10日 14:50 / 商品
帝国データバンクは8月8日、クラフトビールメーカー141社の経営実態調査を発表した。調査によると、前期と比較可能な52社中、「増収」が31社と約6割の企業が売り上げを伸ばした。
反面、税引き後利益では前期との比較が可能な29社のうち、「改善」が14社に対して「悪化」が12と拮抗した。悪化の要因としてもっとも大きいのは人件費の上昇であった。
麦芽やホップなどの原料高、設備増強に伴う償却負担の増加や資材高騰の影響、宣伝広告費の増加や配送費の上昇も利益を圧迫した。
これらは成長のための先行投資という面もあるが、売り上げの伸びに比べて採算面ではやや厳しい状況となっている。
クラフトビール製造を「主業」とするメーカーは54社あった。そのうちの9割は売上高10億円未満で、7割が従業員 10人に満たない、小規模な事業者が中心となっている。
本業は別にあり、クラフトビール製造も手がける「従業」メーカー87社中、本業としてもっとも多いのは「清酒製造」の13社(構成比14.9%)となった。
次いで、「西洋料理店」の11社(同12.6%)で、以下、「酒場、ビヤホール」の9社(同10.3%)、「蒸留酒・混成酒製造」の7社(同 8.0%)、「旅館・ホテル」の6社(同 6.9%)が続いた。
醸造技術を生かして日本酒、ビール製造をともに手がけるメーカーが多いほか、レストランやビヤホールなどにブルワリー(醸造所)を併設、集客の目玉として客単価の上昇に生かしている飲食業者が多い。
「地域」別では「関東」、「中部」、「近畿」の三大都市圏が全体の半分以上を占めたが、「都道府県」別では主業メーカー54社中、「北海道」が8社、構成比14.8%を占めてトップ。第2位は「静岡県」で、第3位は「東京都」となった。
2017年の酒税法改正で安売り規制が強化されて値上げが浸透、2018年春には麦芽使用比率67%のビールの定義が変更され、果実や香辛料などのフレーバーを副原料とした多様な商品開発ができるようになった。
今後は、2026年までの段階的な酒税の一本化によって、ビールの税額が減少する一方、第三のビールや発泡酒の価格面での優位性は失われていくことになる。
ビール市場そのものは縮小が続き、競争は厳しいが、見方を変えればこれらの市場環境の変化はクラフトビールメーカーにとっては大きな追い風になり得る。
ビール系飲料の中でも高価格帯に位置し、個性的な味わいを最大の差別化ポイントとするのがクラフトビールだからだ。
この数年間の知名度向上、存在感の高まりはメーカー各社の企業努力の賜物だろう。
もっとも、クラフトビールがビール市場全体に占める割合はまだまだ微々たるもの。大手も本格的に参入してきた今後の動向がどうなるか、注視したいという。
■クラフトビールメーカー141社の経営実態調査
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p180803.html
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。